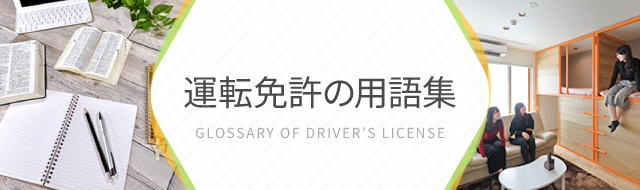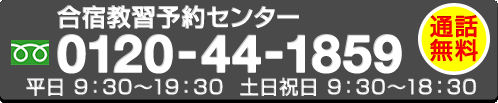運転免許の用語集 あ行
「あ」から始まる用語を紹介するページです
「あ」から始まる用語
ICカード免許証 |
|---|
| 公安委員会が交付する資格証明。偽造防止やプライバシー保護、手続きの円滑化などを目的として、埋め込まれたチップに情報を記録した運転免許証。 本人の顔写真と、氏名・年齢・住所・免許の種類などが記載される。 有効期間の記載部分は、取得年数や違反の有無などによって色が異なる。 |
合図 |
|---|
| あらかじめ決めた方法で相手に知らせること。運転中は方向指示器や手による合図がある。 |
暗順応 |
|---|
| 順応とは、環境の変化に慣れることをいい、人間の目でも起こりますが慣れるまで多少時間がかかるので注意が必要です。明るい場所から暗い場所に移動すると、最初見えなくなり、その後少しずつ見えるようになります。これを暗順応といいます。 |
安全運転管理者 |
|---|
| 一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。運転者に安全な運転をさせるようにしなければなりません。その他にも、交通安全教育を行うことや、運転者の適正、技能、知識や交通規則を守っているかを把握するための処置をとらなければならない。 |
安全確認 |
|---|
| 危険がなく安心ということをはっきり認める。 |
安全空間 |
|---|
| 運転中に危険が生じても安全を保つことができるスペースを安全空間といいます。安全運転をしていても、他の運転者の起こす事故に巻き込まれることがあります。そのような事故を防ぐためにも安全空間が必要です。 |
安全地帯 |
|---|
| 路面電車に乗り降りする人や横断している歩行者の安全を図るために道路上に設けられた島状の施設や、標識と標示で示された道路の部分をいいます。歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければなりません。 |
案内標識 |
|---|
| 地点の名称・方面・距離などを示して通行の便宜を図ろうとするものです。 |
「い」から始まる用語
行き違い |
|---|
| 人や物がすれ違って出会わないこと |
一時停止(指定場所における~) |
|---|
| 走行中の自動車などが標識に従って、いったんその場に止まること。 |
一方通行 |
|---|
| 車両などの通行を道路の一方向に限って許すこと。一方交通。 |
違反者講習 |
|---|
| 本来、前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合、免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば、行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。これを「違反者講習」と呼びます。講習の通知をうけてから一ヶ月以内に違反者講習を受けると停止処分が行われません。講習の内容には交通安全活動などの社会奉仕も選ぶことが出来ます。 |
インターチェンジ |
|---|
| 複数の道路が交差する、または近接する箇所においてその道路の相互を連結するランプを設けて、これらの道路を立体的に接続する構造になっている道路。 |
「う」から始まる用語
右折 |
|---|
| 複数の道路が交差する、または近接する箇所においてその道路の相互を連結するランプを設けて、これらの道路を立体的に接続する構造になっている道路。 |
運転 |
|---|
| 道路で車や路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいいます。 |
運転計画 |
|---|
| 到着時間、所要時間、目的など余裕をもって行動できるよう運転前に前もって計画を立てておくこと。 |
運転経歴証明書 |
|---|
| 過去に失効した免許や取り消された免許又は現在受けている免許の種類や取得年月日等について証明するもの。大型免許や第二種免許の受験で必要な場合がある。 |
運転姿勢 |
|---|
| 運転姿勢とは、運転に必要な操作ができる姿勢です。 |
運転適正検査 |
|---|
| ドライバーが自分の性格や癖を知るための方法として開発されたものが、運転適正検査です。これは運転に影響を与えやすい個人の特性を科学的に測定、分類する心理検査の一種で主なものに「警察庁方式運転適性検査K型」「OD式安全性テスト」「IDP運転適正検査」などがあります。 |
運転免許(~のしくみ) |
|---|
| 運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。 このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。 |
「え」から始まる用語
エアバック(~システム) |
|---|
| ハンドルの中央部やダッシュボードなどに仕込み、時速30㎞以上の速度でコンクリートなどの固いものに衝突したときに作動します。 |
ABS(アンチロック・ブレーキシステム) |
|---|
| 急ブレーキをかけたときにコンピューターで自動制御し、車輪のロックを防ぐシステムです。これにより横すべりを起こしたり、ハンドル操作がきかなくなるといった現象を防げます。正常に作動するとブレーキペダルに小きざみな振動(キックバック現象)が感じられます。 |
エンジンブレーキ |
|---|
| 自動車の走行中にアクセルペダルを離すことによっておきる制動作用。エンジンの回転が落ち、摩擦や圧縮抵抗が生じて駆動輪を制動します。下り坂の道や高速道路では通常ブレーキと併用。 |
遠心力 |
|---|
| 回転運動をする系において観測される慣性力の一種で見かけ力である。円運動のある時点での接線方向に働く慣性力と円軌道との差異が回転の中心から見て外側へと向かう方向に力が加えられているように見え、遠心力という力が働いているように感じる。 |
「お」から始まる用語
追い越し |
|---|
| 車が進路を変えて、進行中の車の前方に出ること。 |
追い抜き |
|---|
| 車が進路を変えずに、進行中の車の前方に出ること。 |
応急用タイヤ(スペアタイヤ) |
|---|
| パンクなどの緊急時に備えて自動車に取り付けてある臨時用タイヤ。トランクや車体の下などに設置されている。使用しているタイヤと同様のタイヤが備え付けられていることもあるが、標準タイヤより空気圧が高く直径や幅がやや小さいタイヤが備えられていることもある。 |
横断(~禁止) |
|---|
| 車は、他の歩行者の通行や他の車などの正常な進行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回、後退をしたり道路に面した場所に出入りするために右左折や横断してはいけない。 |
横断歩道 |
|---|
| 道路標識や道路標示によって歩行者の横断のための場所であることが示されている道路の一部。 |
大型自動車 |
|---|
| 自動車の区分のひとつで、車両総重量11.000㎏以上、最大積載量6.500㎏以上、乗車定員30人以上の四輪者のこと。大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許でのみ運転することができる。 |
大型自動二輪 |
|---|
| 一般的に排気量400㏄を越えるバイクのこと。大型二輪免許で運転でき、高速道路も走行できる。 |
大型特殊自動車 |
|---|
| 自動車の区分の中で、特殊な形状構造をした自動車をいう。一般的に表現すると、作業機を取り付けた車両で、走行や運搬よりも、その作業機を使うことが目的の自動車。運転席と作業機の操作台は同じである。ショベルやロータリ除雪車等。 |
大型二輪免許(AT限定の~) |
|---|
| 運転できる二輪車(大型自動二輪車・普通自動二輪車)は総排気量650㏄以下のオートマチック車に限られます。 |
大地震 |
|---|
| マグニチュード7以上の地震のこと。 |
オートマチック二輪車 |
|---|
| オートマチック(AT)車には、スピードやパワーに合わせてギアを自動的に切り替える機能があるのでマニュアル(MT)車のようにいちいちペダルを踏んでギアチェンジをする必要はありません。 |
オーバーヒート |
|---|
| 空冷エンジンで、冷却が追いつかずにエンジン適温を上回っている状態。サ-キットなどで連続高回転の走行を続けたりラジエータのクーラント漏れなどでおきる。オーバーヒートの警告灯が点灯した場合、そのまま走行を続けると最悪エンジンの抱きつきや焼きつき、ガソリンエンジンだと自然発火によるバルブからのバックファイヤが起こるため、すぐさま停止してエンジンを冷却する必要がある。 |